保育士がワークライフバランスを保つにはどうする?
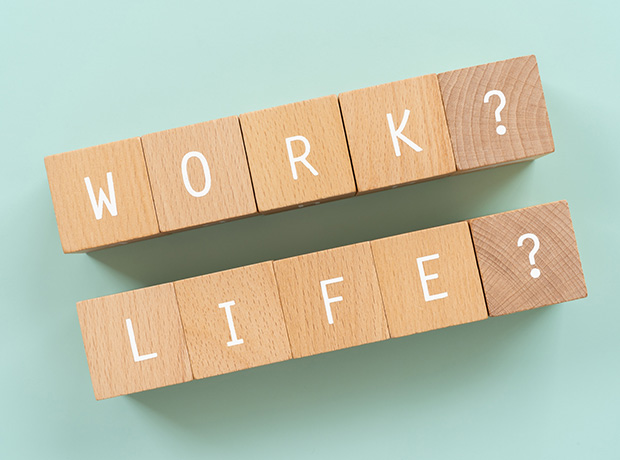
働き方改革の推進という国の動きもあり、社会全体が「ワークライフバランスを保ちながら働く」という方向にシフトしています。保育士も例外ではありません。ただ、現実を見据えると難しい面があることも事実です。保育士がワークライフバランスを保つには、どうしたらよいのでしょうか。この記事で、そのヒントをお伝えします。
ワークライフバランスとは?
ワークライフバランスというのは、国が推進する施策のひとつで、長時間労働が問題視され始めたころに登場した言葉です。具体的には、2007年発表の文書「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に、ワークライフバランスの考え方が提示されました。以降、現在に至るまで、さまざまな取り組みが行われています。
例えば内閣府は「令和元年度 ワークライフバランス推進強化月間における取組」で、以下の4項目を掲げました。
- 長時間労働の是正
- 働く場所と時間の柔軟化による多様な働き方の推進
- 休暇等の取得促進
- 職員の意識改革に向けた支援
2は「テレワーク」「ワーケーション」など、4は「男性の産休・育休取得」などが挙げられます。
まとめると、これらの項目を意識しながら、仕事とプライベートのバランスが取れた生活を送ろうということです。
ただ、保育士の場合、テレワークは現実的ではありません。それぞれの働き方の中で、どのように対応していくかが、今後の課題ともいえます。
ワークライフバランスが崩れるとどうなる?
国がワークライフバランスを提言する背景にあるのは、それが崩れたときに起こるリスクがあるからです。具体的にどのようなリスクがあるのか、見ていきましょう。
まず長時間労働です。長時間労働は、言うまでもなく体を疲れさせます。それにより健康状態が悪化すると、意欲や正常な判断力が低下し、仕事に必要以上の時間がかかったり、ミスが続いたりということも。状況によっては、長期的に仕事を休んで療養せざるをえなくなります。こうなってくると、仕事だけでなく生活にも影響が及ぶことは必至です。
また、小さな子どものいる家庭でどちらか一方が長時間労働をすると、育児や家事の負担は、必然的にもう一方にかかります。家族サービスもままならず、家庭がギクシャクしがちに……。育児ではなく、介護する人がいる場合も同じことがいえます。
さらに、女性が結婚した場合、ワークライフバランスが取れないと「退職」という選択をせねばなりません。働きたいという意欲があり、社会でも人手不足が叫ばれているのに働けないというのは、大きなリスクのひとつと言えるのではないでしょうか。
保育士がワークライフバランスの均衡を保ちづらい理由

保育士は、ワークライフバランスが取りにくいといわれています。すでに保育士として働いている人は、実感しているのではないでしょうか。ではなぜ、バランスが取りにくいのか、理由を考えてみましょう。
まず、勤務時間の不規則さが挙げられます。開所時間は保育園により異なりますが、働く親の子どもを預かるという性質上、朝は7時もしくは7時30分に開けるという園がほとんどです。終わりは18時か18時30分に設定しているところが多く、ざっくり計算すると、11時間は開所しているという計算になります。中には延長保育などで21時前後まで開けているところも少なくありません。
開所時間が11時間を超えつつ、労働基準法に定められた労働条件をクリアするために、多くの保育園では「早番」「遅番」などのシフト制を採用しています。しかし、あるときは7時出勤、あるときは12時出勤というシフトではプライベートの予定が組みにくく、どうしても仕事重視になりがちです。
有給休暇が取りにくいことも、ワークライフバランスの保ちにくい要因のひとつといっていいでしょう。
先ほどお話したように、保育園は「働く親の子どもを預かる」場であるため、多くの保育園では、月曜日から土曜日の開所が基本です。そうなると、保育士が平日にお休みを取るためには、シフトの調整をする必要があります。ほかの職員も巻き込むことになるということです。そうなると、休みの申請をすることも気が引けてしまいます。なかなか長期休暇を取ることもできないというのが現実です。
さらに、保育以外の業務の多さも、ワークライフバランスを保ちにくくしている要因といわれています。保育時間中は子どもにかかりっきりになりますから、日誌記入などの事務作業、室内装飾の制作物などは、子どもが帰宅して以降の時間帯にせざるをえません。そうなると、保育園に残って残業をするか、持ち帰って家でこなすか――。いずれにしても、プライベート時間に仕事が食い込み、必然的にバランスが崩れるということになってしまいます。
保育士がワークライフバランスを保つには
ワークライフバランスを保つのがなかなか難しい保育士ですが、決してできないわけではありません。工夫しながら、自分なりのスタイルを確立していきましょう。
ひとつは、仕事に優先順位をつけること。絶対に当日中に終わらせなければならないこと、明日でも間に合うこと、数日かけて取り組めばよいことなど、自分が持っている仕事を整理してスケジューリングします。このとき、頭の中だけで考えるのではなく、必ず書き出しましょう。持っている仕事の全貌がつかみやすく「残業しなくても大丈夫」「持ち帰らずに明日やろう」という判断が、すぐにできます。
休日は、心身のリフレッシュを意識して過ごすようにしましょう。仕事を持ち込まないように、あらかじめ休日の過ごし方の計画を立てておくことも効果的です。
家族がいる場合は、協力を依頼してみましょう。家事の分担を見直すだけでも、プライベートの自分の時間を増やすことができます。
また、保育園の労働環境に問題があるという場合は、思い切って転職を視野に入れてみてはどうでしょうか。ワークライフバランスが取れる職場は、探せば必ずあります。
仕事の性質上、どうしても保育士はワークライフバランスを保ちにくい面があります。しかし、不可能というわけではありません。保育士という仕事が好きなら、自分に合ったワークライフバランスの取り方を考え、実行してみませんか? 仕事もプライベートも充実の保育士生活、ぜひ実現しましょう。

